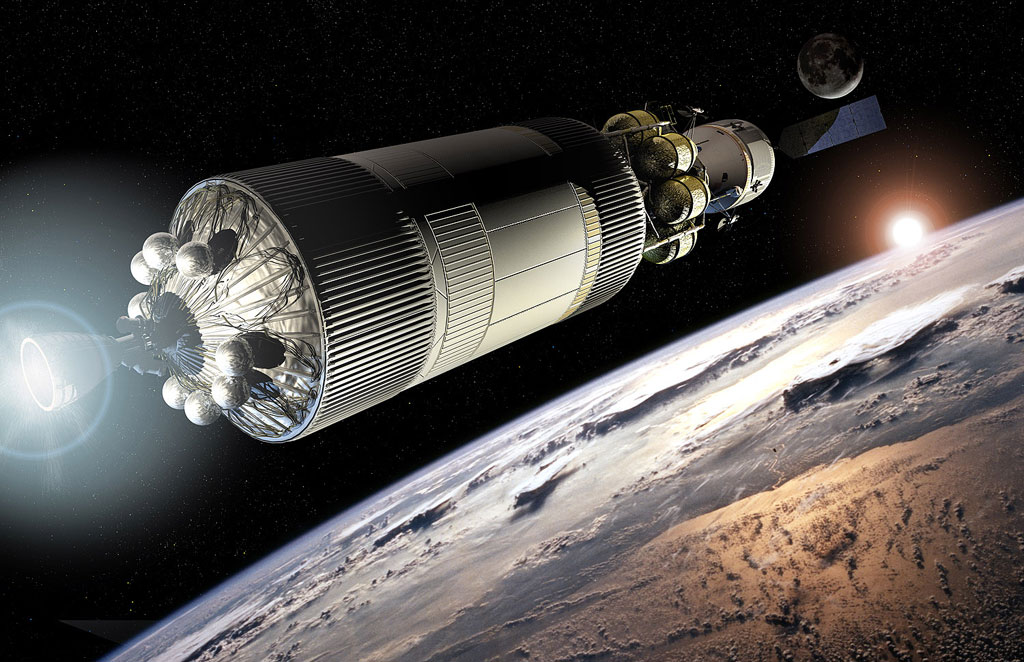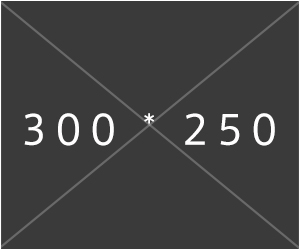現在では広く知られている自律神経ですが、それらはどのように発見、研究されてきたのでしょうか。千葉大学特任教授の朝比奈正人氏のインタビューにてわかりやすく解説されています。以下はインタビューからの引用となります。
「自律神経」について、最初に記載したのは、ギリシャの医学者ガレノス(紀元129 ~ 199年頃)です。ガレノスに自律神経という概念こそなかったものの、当時すでに現在の迷走神経や交感神経に相当する神経の形態について記し、末梢の神経が体のさまざまな部位を つないで交感、同調させていると考えていました。この時の「交感」という概念が今も「交感神経」という用語で残っているのです。
その後、いわゆる科学の暗黒時代を経て、17世紀にイギリスの医師であり解剖学者であるウィリス(1621~ 75年)は、著作で「intercostal nerve」と「wandering nerve」という用語を用い、現在の交感神経幹と迷走神経にあたる神経を解剖学的に記載しました。
18世紀には動物実験によって、神経の生理学的な機能が明らかになってきます。フランスのデュ・プチ(1664 ~ 1741年)は、犬の頸部にある交感神経を切断すると瞳孔に異常が見られることから頸部交感神経が瞳孔を支配していることを証明しましたし、また同 じフランスのベルナール(1813 ~ 78年)は、ウサギの頭頸部の交感神経を切断すると耳の皮膚が紅潮し皮膚温が上昇すること、さらにブラウン・セカール(1817~ 94年)は、交感神経の刺激によって血管が収縮することを突き止めました。
それから少し遅れて、薬理学が発達していきます。
副交感神経の機能を解明するのに役立ったアセチルコリン、アトロピン、ニコチン、ムスカリン、ピロカルピンの分離・生成が成功し、また日本人研究者、高峰譲吉(1854 ~ 1922年)と上中啓三(1876 ~ 1960年)も1906年、アドレナリンの結晶の抽出に成功するなど、大きな進歩がありました。これらの物質の発見を経て、1904年にイギリスのエリオット(1877 ~ 1961年)が交感神経の末端からアドレナリン様の物質が放出されているという仮説を提唱し、アドレナリンが刺激作用を持つとしたことが「神経伝達物質」という概念の発端となっています。
1905年にイギリスのラングレー(1852 ~ 1925年)がニコチンの神経作用の機序として、「receptive substance」、つまり受容体の概念を提唱します。彼は21年に『e Autonomic Nervous System』を著し、「自律神経系」という用語を提示しました。著書では、自 律神経系を胸腰系(交感神経系)、頭仙系(副交感神経系)、腸管系の3つに分け、胸腰系と頭仙系が拮抗する役割を持つことを記しています。解剖学的には運動神経とも感覚神経とも異なる神経を、機能学的、薬理学的な研究の成果とともに検討することによって、共 通する働きを持つ神経系として「自律神経」を浮かび上がらせた、歴史的な成果と言えます。
その後、1920年代にスイスの生理学者ヘス(1881~ 1973年)が、脳の視床下部が自律神経活動に重要あることを明らかにし、49年にノーベル賞を受賞しています。
さらに交感神経からアドレナリン様の物質が発見され、41年にそれをノルアドレナリンと同定したスウェーデンのオイラー(1905 ~ 83年)は、その功績によって70年にノーベル賞を受賞しました。
こうして自律神経の概念が確立しましたが、特にラングレーの著作が非常に優れていたこともあり、交感神経と副交感神経の拮抗によって自律神経が機能するという考え方は、広く現代まで浸透しています。
全文は下記よりお読みいただけます。
https://www.noushinkeinaika-t.com/wp-content/uploads/p02_05.pdf